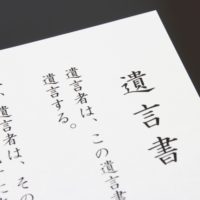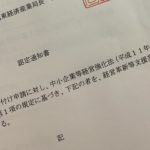特例事業承継税制 (従来の事業承継税制との違い)
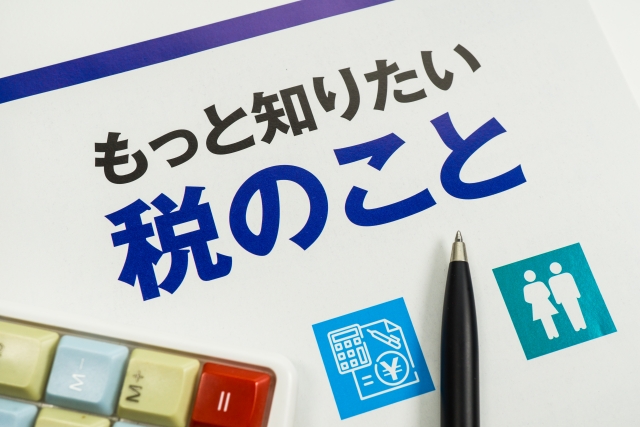
今回は、平成30年4月から始まった特例事業承継税制と従来の事業承継税制を比較してみます。
なお、従来の事業承継税制も生きたままです。特例事業承継税制は、期限や条件が定められており、それに合致しない場合には従来の事業承継税制(この要件を満たすものに限る)を使うことも可能です。
特例事業承継税制と従来の事業承継税制との違い
従来の事業承継税制は贈与税の納税猶予対象とされるものが発行済議決権株式総数の3分の2までとなり、残り3分の1は適用対象外でした。さらに納税猶予となるのはその評価額の80%に対応する税額です。また、適用を受けてから5年間の事業継続要件があり、特に雇用確保要件が大きなリスクでした。その他にもさまざまなリスクや不便さがありましたが、これらが特例事業承継税制では解消されています。
特例事業承継税制(平成30年4月)による変更点
(1)事業承継税制の対象株式が100%に
(従来)発行済議決権株式総数の3分の2が限度
(特例)発行済議決権株式総数の100%、全てが対象
(2)相続時に納税猶予される相続税額の適用対象が株式評価額の100%に
(従来)適用対象となる株式の評価額の80%に相当する金額に対応する相続税額
(特例)同評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額
(3)雇用確保要件の実質撤廃
(従来)
贈与又は相続から5年間の事業継続期間中に一定の要件を満たさなくなると認定取り消し、猶予税額全額納税が必要。その要件のひとつが雇用確保要件で、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回らないこと。
(特例)
上記80%を下回った場合、認定経営革新等支援機関の意見が掲載された「下回った理由を記載した書類」を提出すれば認定は取り消されない。
(4)複数の株式所有者からの贈与が可能に
(従来)
代表者であった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与に限られていました。
(特例)
先代経営者からの一括贈与を条件に、後継者が特例認定承継会社の代表以外のものから贈与等により取得する特例認定贈与承継会社の非上場株式についても、特例経営承継期間(5年)内にその贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、対象とされます。つまり、役員になったことのない株主でかつ親族以外の人から贈与を受けても適用を受けられます。なお、現行の事業承継税制においてもこの点は改正され適用可能となります。
(5)受贈者の範囲拡大
(従来)
適用対象となる後継者は筆頭株主である代表者に限られています。
(特例)
特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名又は3名が対象となります。
(6)推定相続人以外でも相続時精算課税の適用を受けることが可能に
(従来)
相続時精算課税の適用対象者は推定相続人と孫のみ
(特例)
推定相続人と孫以外の親族や第三者でも相続時精算課税の適用を受けて非上場株式等の贈与税の納税猶予の適用が受けられる。
(7)特例経営承継期間経過後の減免
(従来)
民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除される規定があります。
(特例)
譲渡時、合併による消滅時及び解散時に同様の制度が導入され、一部減免されます。譲渡や合併による消滅の場合には相続税評価額の50%を下限として計算します。
(8)特例承継計画の提出
(従来)
使いやすく、有利になりリスクも大幅に減少した特例事業承継税制の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて会社が作成した「特例承継計画」の都道府県への提出が必要です。提出期限は平成30年4月1日から平成35年3月31日までとなっています。
特例承継計画の作成にあたってはお問合せフォームからお問い合わせ下さい。